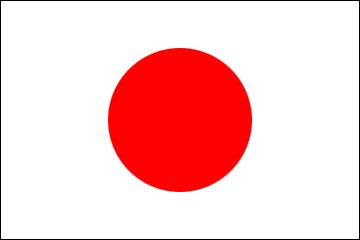令和6年度イスラム寄宿塾教師招へい
令和6年12月23日
日本政府は、日本とインドネシアのイスラム社会との相互理解を深めることを目的に、2004年度からイスラム寄宿塾(プサントレン)教師招へい事業を実施してきました。本年度は、東ジャワ州、南カリマンタン州、南スラウェシ州、中部スラウェシ州出身の塾長及び教師5名と国立イスラム大学イスラム社会研究所研究員1名が12月3日から12月11日まで訪日しました。
訪日中、招へい者は東京、京都に滞在し、初等教育機関、農業高校、大学や寺社等を訪問し、日本の教育や歴史、宗教や農業について意見交換を行いました。招へい者からは、自立性を育成する初等教育の実践と規律の正しさを称賛する感想が述べられたほか、京都妙心寺や東京浅草神社での宗教間対話を通して、それぞれの違いを乗り越え、宗教間の調和を築く方法について再考する機会を得たとの意見が聞かれました。また、茶道体験やホームステイを通して日本の文化を体験したことは、参加者にとって貴重な異文化体験となりました。
12月11日には帰国報告会を開催し、招へい者6名や国立イスラム大学関係者等の来賓、また当館からは永井次席公使等が出席しました。永井次席公使は挨拶において、本年インドネシアに新政権が成立したことを踏まえ、日本政府として、人的交流を含む様々な分野でインドネシアとの協力を一層強化していく考えであることに言及するとともに、今回の訪日で参加者が体験し、学んだことを各プサントレンの教育活動において活かしてほしいとの期待を伝えました。
帰国報告会で、参加者を代表して南カリマンタン州のキキ・ムスタキマ氏は、各訪問先・行事で撮影した様々な写真を紹介しつつ、「小学校での給食の配膳で規律正しく列に並ぶ生徒たちの様子、そして、自分の食事の準備が終わって他の生徒を待っている間、本を読む生徒が多かったことがとても印象に残った。」と述べました。また、もう一人の報告者である東ジャワ州のリドワン・バイドロウィ氏は、日本の人格教育のよい部分を取り入れて、それぞれのプサントレンで抜本的な変容を促していきたいとの意欲を示しました。他の参加者4名も、学生の礼儀や規律の正しさ、小学校で家庭科教育を実践していることへの驚き、などについて印象を述べました。
来賓として挨拶したジャムハリ・マルフ国立イスラム大学イスラム社会研究所長は、今回の招へい者6名が訪日を通して有意義な経験を得たと述べ、「日本社会から見習うべき点は各プサントレンにおいて積極的に取り入れ、活かして欲しい。」と伝えました。
 帰国報告会
帰国報告会
 都立農業高校
都立農業高校
 京都福寿園での茶道体験
京都福寿園での茶道体験
 妙心寺退蔵院での宗教間対話
妙心寺退蔵院での宗教間対話