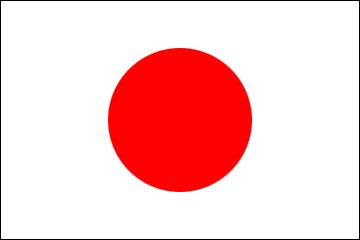日インドネシア高等教育協力をより強化する
(ラクヤットムルデカ紙、8月22日(金)朝刊に掲載)
7月10日、マカッサルのハサヌディン大学において、日本とインドネシアの大学間交流促進を通じた両国の国際的地位向上とネットワーク構築を目的として、第6回日インドネシア学長会議が開催されました。本会議には、私も出席し、両国の高等教育機関の交流の重要性について講演を行いました。
現代社会は、気候変動、資源枯渇、感染症といった地球規模課題の解決が複雑に絡み合い、国境を越えて多様な文化や知見を持つ人材による国際協力が不可欠な時代となりました。大学間交流は、国際的な視野を持つ人材育成と最先端の研究開発を推進する上で、その役割はますます重要になっています。この認識を共有し、日インドネシア両国は高等教育分野における協力を一層強化していく必要があると確信しております。
両国の関係は、歴史的に深い人的交流によって支えられてきました。戦後の賠償留学生から始まり、多くのインドネシア人が日本で学び、その経験を母国の発展に活かしてきました。現在でも、71万人もの日本語学習者が存在するインドネシアにおいて、日本との友好関係を築く基盤は極めて強固であると実感しています。
インドネシアと日本の政府は、大学間交流の促進を最重要課題の一つとして位置づけています。今年1月の首脳会談においても、プラボウォ大統領と石破元首相は、人材育成の重要性と双方向の交流強化で一致しました。政府レベルでの強い意志が示されていることは、大変心強く感じています。
日本の外国人留学生受け入れ目標(2033年までに40万人)や、東南アジア地域を重点地域とする政策、そしてインドネシアからの我が国高等教育機関への留学生数の増加(2024年5月時点で5,397人、世界8位、10年前比1.8倍)といった現状を踏まえつつも、戦後の多くのインドネシア人留学生の活躍を知る者として、更なる留学生数の増加への期待を強く持っています。日本人学生の海外留学者数も、2024年度には前年度比53.3%増の89,179人となり、大幅な回復傾向にあります。これは、コロナ禍で一時的に停滞していた海外留学が、入国制限の緩和に伴い活発化してきたことを示しています。
こうした良好な状況をより加速・発展させるためには、両国間での大学同士の交流を活性化していくことが不可欠です。特に、ジョイント・ディグリーやダブル・ディグリー等単位認定が伴う多様な形態で、教育的価値の高く、国際的な視野を持つ人材育成にも貢献できる取組を進めていくことが重要と考えます。最新の数値では、日本とインドネシアの大学は1,882件の大学間交流協定を締結し、47の日本の大学がインドネシア国内に拠点を設置しています。これらの取組は、両国の大学間の連携を強化し、活発な交流を促進するための重要な基盤となっています。これらの基盤の活用を促進していくため、協定に基づく具体的な交換プログラムの策定、拠点の機能強化、情報共有の促進などが重要と考えます。
日本の岡山大学は、東南アジア地域を留学生交流強化の重点地域として位置づけた文部科学省より委託を受け、ジャカルタ近郊のダルマ・プルサダ大学学内、インドネシア大学学内及びスラバヤに事務所を設置し、岡山大学以外の大学を含めた日本の大学への留学生獲得を推進するための活動を行っています。引き続き、在インドネシア日本国大使館としても、岡山大学と連携しながら、両国の大学間交流の強化に尽力して参ります。
さらに、科学技術分野における協力についても、大きな期待を寄せています。SATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)による共同研究プロジェクトは、両国の科学技術レベル向上と地球規模課題解決に貢献する取り組みとして、高く評価しております。また、日ASEAN科学技術・イノベーション共同連携事業(NEXUS)における「バイオものづくり」分野での協力にも、大きな可能性を感じています。
インドネシアの大学が、多くの人材を日本の産業界に輩出していることも注目に値します。スラバヤ国立大学における積極的なインターンシップの取り組みは、好例と言えるでしょう。日本在留するインドネシア人技能実習生・特定技能労働者は、近年、急激な増加傾向にあり、ベトナムに次いで世界で2番目に多い合計15万人に達しており、2年後に開始される新しい育成就労制度も、インドネシアの若者の活躍の場を広げるものと期待しています。
コロナ以降初めて開催となった本会議には、両国から、前回の69校を大きく上回り、88もの高等教育機関の幹部が出席しました。日インドネシア大学間交流は、両国の未来を創造するために不可欠です。大学同士が連携し、一体となって取り組むことで、両国間の友好関係を深め、共に持続可能な社会を実現できると確信しています。今回の学長会議が、その連携を活性化する重要な契機となり、両国の絆がよりいっそう深まっていくよう、我々も取り組んで参ります。
正木靖
駐インドネシア日本国大使
https://rm.id/baca-berita/internasional/278211/memperkuat-kerja-sama-pendidikan-tinggi-jepangri
公館案内
- 在インドネシア日本国大使
- 大使の活動
- 公館案内
- 電話番号・住所、地図
- 開館時間
- 休館日
- 国内総領事館管轄地域